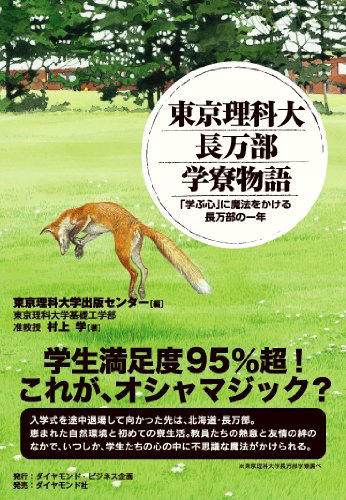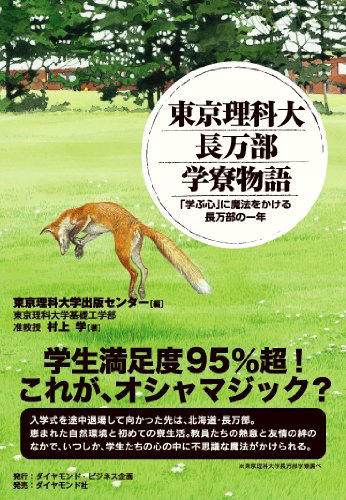――まずは、この『長万部学寮物語』の出版のきっかけを教えてください。
村上氏(以下、村上) 以前から従来のパンフレットでは全寮制で我々がやっていることが伝わらないという意見がありました。逆に、これだけすごいことをしているのだから、もっと広く宣伝するべきだというご意見も多かったのです。それに、この数年、大学でも社会に向けてさまざまな情報発信をしていこうという気運が高まっていました。で、昨年ですが、現在の学長がこうなったら「出しなさい」と(笑)。ちょうどパンフレットの企画に携わっていた私が執筆代表者ということになりました。
――なるほど。では、この本はパンフレットの発展形、ということなのですね。ということは、やはり読んでもらいたいのは、これから大学へ進学する受験生たちでしょうか?
村上 そうですね。まずは大学進学を控えたお子さんを持つ保護者のみなさんに読んでいただきたいと思います。大学の教育については色々なイメージがあると思うのですが、おそらくご自身が経験された学生生活とはひと味違った時間を、もしお子さんが入学したらここ長万部キャンパスで過ごせることが分かっていただけるのではないかと思います。是非、理科大学と基礎工学部の良さを伝えたいです。
また、教育関係者の方にも読んでいただければと思います。我々としては、本書でこんな教育をしていますという実践事例を提示することになります。特に「教養教育」の再評価と見直しが進んでいる現在、ご批判も含めてご意見をいただければ本当に嬉しいです。長万部キャンパスでは現在でもより好い教育を模索し続けて試行錯誤を重ねていますので、是非参考にさせていただければと思います。
あとは卒業生ですね。今年度(2011年度)で25期目を迎えますが、卒業生だけでもすでに長万部町の人口(約6000人)を超えています。経験者にしか分からないコネタも入れていますし、それぞれのエピソードについて私の時もそうだったとか、こんなことはオレの時はなかったとか、楽しんでもらえたら好いなと思います。
――本書を執筆するにあたり、こだわったことはありますか?
村上 登場人物はもちろん架空で、物語全体はフィクションですが、パンフレットとして「事実」は曲げないように気をつけました。地理的環境や設備などは現実の長万部です。それこそキツネの穴の位置も実際にある場所にしています。だから、主要な登場人物四人が経験したことは、これからやってくる寮生の誰もが経験できる可能性があります。
――由佳、夏帆、壮太、努の四人の主人公たちが、とても生き生きと描かれていますが、彼らは特にモデルの学生さんがいるわけではなく、架空のキャラクターなんですね?
村上 はい。キャラクターの設定は担当編集者と何度も議論を重ねました。この物語は、そうやって設定されたキャラクターが入寮したらきっとこういう経験をしてこんな風に感じて、そしてこんな風に変わっていく、という形で書き進められています。いわばシミュレーションですね。理系の大学らしいアプローチかもしれません(笑)。
――最後に、村上先生が寮運営に携わり、日々学生たちと接するにあたって、日頃大切にしていることがあれば教えてください。
村上 まずは安全と健康です。ありきたりですが、それが日々の生活の基盤ですから。その上で、彼らが長万部でしか体験できない充実した時間を過ごせるようにできる限りのことをしたいと思っています。ただし、教職員や事務職員にできることは限られていますから、むしろ学生たちが自分たち自身で成長できるような環境や仕掛け作りをきちんと整えることをより大事にしています。ですからあらためて考えると、手を出すところと出さないところの塩梅を間違えないようにするところに神経を使っているかもしれません。他には、自分自身が長万部の四季や学生に対して新鮮さを失わないというのは大事ですね。なので、研究室にある前年度の学生の痕跡は3月にできるだけ消して、4月の新年度を迎えるようにしています。ただ、どうしても過去の学生と比較してしまいがちですけれど。最後に、必要以上に仲良くならないってことですかね(笑)。2月の退寮の時期がつらいので。結局一年で学生はみんないなくなります。置いてきぼりを食らったかんじで本当に身に応えますから。
村上学(むらかみ・まなぶ)
東京理科大学 基礎工学部 准教授。九州大学文学部哲学科卒業。
九州大学 文学研究科 哲学 修士・博士修了。その後、東京理科大学基礎工学部の准教授となる。
専攻は、哲学・倫理学。
長万部赴任後、寮の運営に携わり、2011年度は「学寮運営委員会」の委員でもある。
現代GPプロジェクト推進委員会委員(2007~2009年度)
著書に「会話と思考の作法」(創言社)がある。