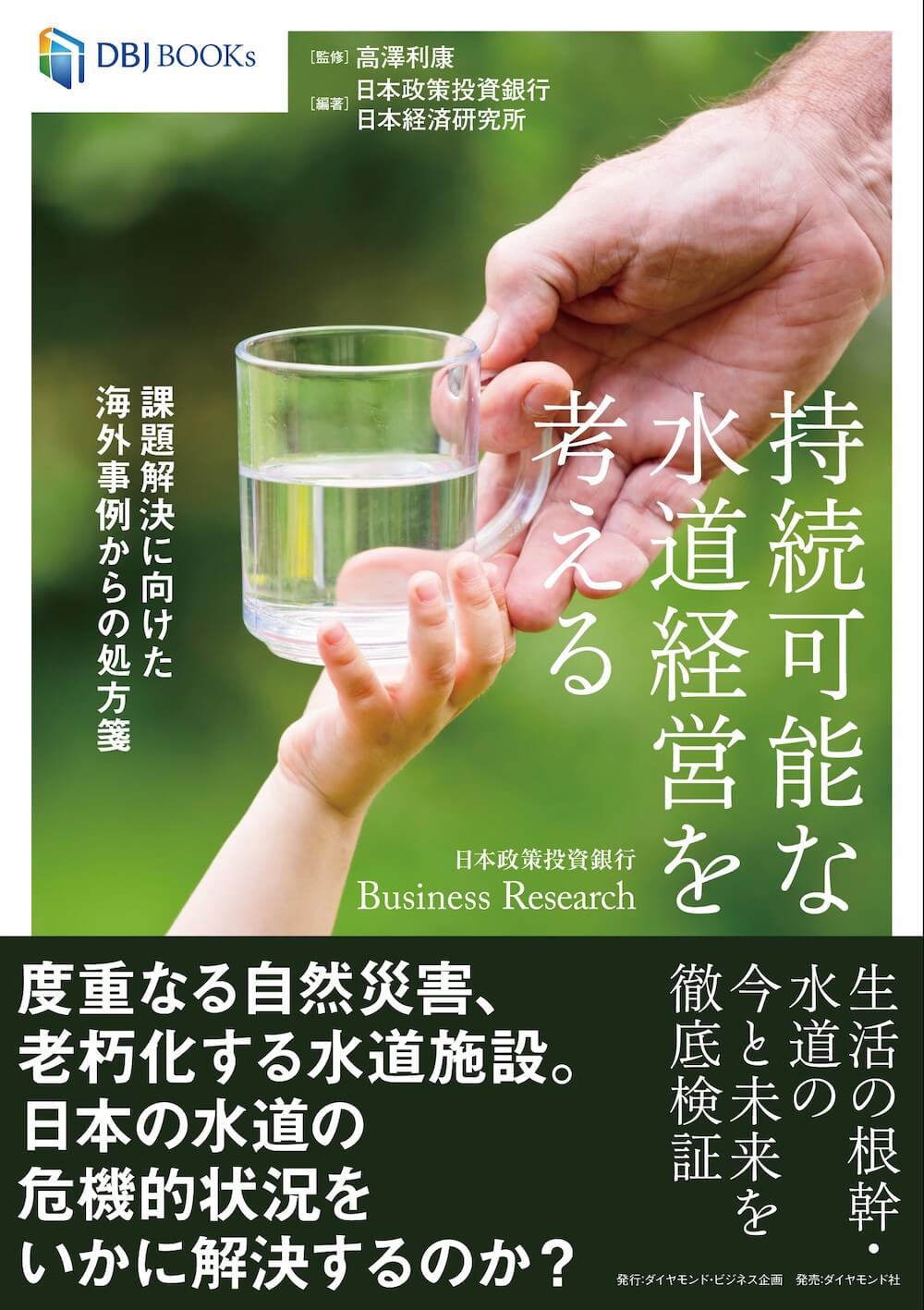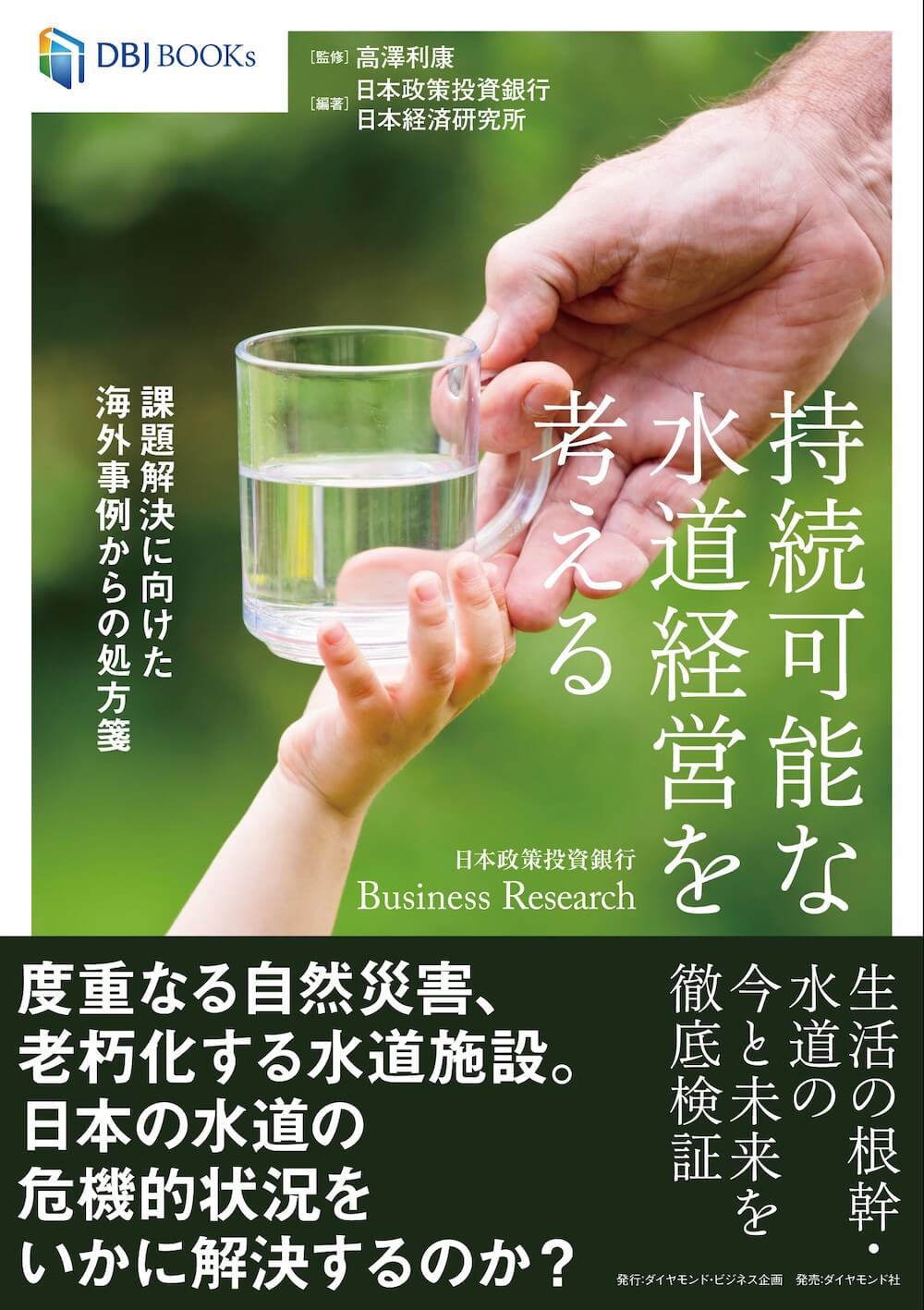――日本の上下水道事業の歴史や概況について教えてください
宮川暁世氏(以下、宮川) 日本で最初の近代水道(上水道)は、1887(明治20)年に横浜で整備されました。以来、約140年にわたる歴史の中で生活や経済活動に欠かせない社会資本として定着しています。
また近代下水道の始まりは、1881年に横浜で、1884年に東京・神田で建設された下水道に遡ります。上水道・下水道ともに、高度成長期に急速に整備が進められた結果、現在では水道及び汚水処理人口の普及率はいずれも90%以上を推移しています。
一方で、法定耐用年数を超えた管路等の上下水道施設が年々増加していますが、適切な更新や耐震化が進んでいないことから、漏水や破損事故が全国で発生しています。2014年の「国土交通白書」では“これからの社会インフラの維持管理・更新に向けて”とのテーマが掲げられ、日本における社会インフラを取り巻く環境変化や維持管理上の課題が大きく注目されるようになりました。
2025年1月には、埼玉県八潮市内で流域下水道の下水道管の破損に起因すると思われる道路陥没事故が発生しましたが、改めて社会インフラの老朽化問題の深刻さが認識された出来事でありました。
――日本では「水道料金は一律」というイメージがあるのですが、そうではないのでしょうか?
宮川 国内における上下水道事業は、地形などの地理的な違い、水源や排出水域の違い、人口規模や都市の成り立ちの違い等から、経営上の課題も様々です。結果として上下水道の料金水準に大きな差が生じています。
清廉かつ豊富な水源を有していない事業体では、薬品処理等による水処理に係るコストが嵩み、また行政区域内に人口が分散している場合は、より長い管路の敷設が必要となり、人口当たりの管路敷設費用が高くなる傾向にあります。
さらに、全国の上下水道事業は、軒並み老朽化に伴う更新を迎えていることから、今後の更新投資費の増大が想定されています。一方で人口減少により大きな収入増は見込めず、むしろ節水機器の普及等によって使用水量が減り、収入が減少して財政状況がより厳しくなることは明らかな状況です。
上下水道料金については、法制度上は「総括原価方式(対象経費に適正利潤を上乗せして料金が決定するもので、安定した供給が求められる公共性の高いサービス事業に適用される)」であるものの、地域独占事業でもあります。料金設定や値上げに当たっては慎重な判断が求められ、実際の手続きにおいては地方公共団体の議会承認が必須です。
そのため、今までは値上げを回避するため、老朽化に対応するための更新投資を後ろ倒しにする等の対応で凌いでいたものの、いよいよ投資の先送りでは対応できない状況となってきています。
――最後に、読者の皆さまにメッセージをお願いいたします。
宮川 私たちが生活インフラとして当たり前のように利用している上下水道は、その水循環を健全に保つために長年にわたり培われた技術的な蓄積と、すべての人が等しく恩恵を受けられるようにという公益的な理念によって質の高いサービスが維持されてきました。
しかし、上下水道の整備が一巡し、人口が減少に転じ始めた近年では、施設老朽化に対応するための多大な投資や職員減少による労働力確保の困難さ、利用者減少に伴う収入減といったマイナスのスパイラルへと様相が変化しています。
さらに、近年は気候変動により頻発化、激甚化している豪雨への対応が一層求められるとともに、地震等自然災害を想定した強靭化も引き続き推し進める必要があります。2024年に発生した能登半島地震は、上下水道をはじめとする社会インフラに甚大な被害をもたらしました。完全な復旧には時間を要している状況であり、人的リソースの制約がある中で社会インフラの復旧をどこまで優先的に行うべきかという点も議論になっているところです。
これからの社会インフラの課題解決には、サービスを提供する側の公共、民間事業者が、スピード感を持って新たな施策に対応することが求められます。また、サービスを受益する利用者においても、施設の維持管理のために料金値上げ等の負担が生じること等、上下水道が直面している現状課題の理解を深める必要性があります。
本書でご紹介した事例や試みが、少しでも上下水道事業における新たな取り組みへ一歩踏み出す一助になれば幸いです。
株式会社日本政策投資銀行
「金融力で未来をデザインします」を企業理念に掲げ、中立的かつ長期的視点にたち、投融資一体型のシームレスな金融サービスを提供している。また、地域課題解決や地域活性化・地域創生へ向けて、国や地方公共団体、民間事業者、地域金融機関などと連携・協働しつつ、各種調査・情報発信・提言やプロジェクトメイキング支援などに幅広く取り組んでいる。
株式会社日本経済研究所
日本政策投資銀行グループの一員として、上下水道事業やスポーツ施設分野でのPPP/PFIなどの官民連携、空港やガス事業などのインフラ民営化、公共施設マネジメントなどの分野に関する調査・コンサルティングを幅広く実施し、地方公共団体や地域企業への取り組みにも力を注いでいる。