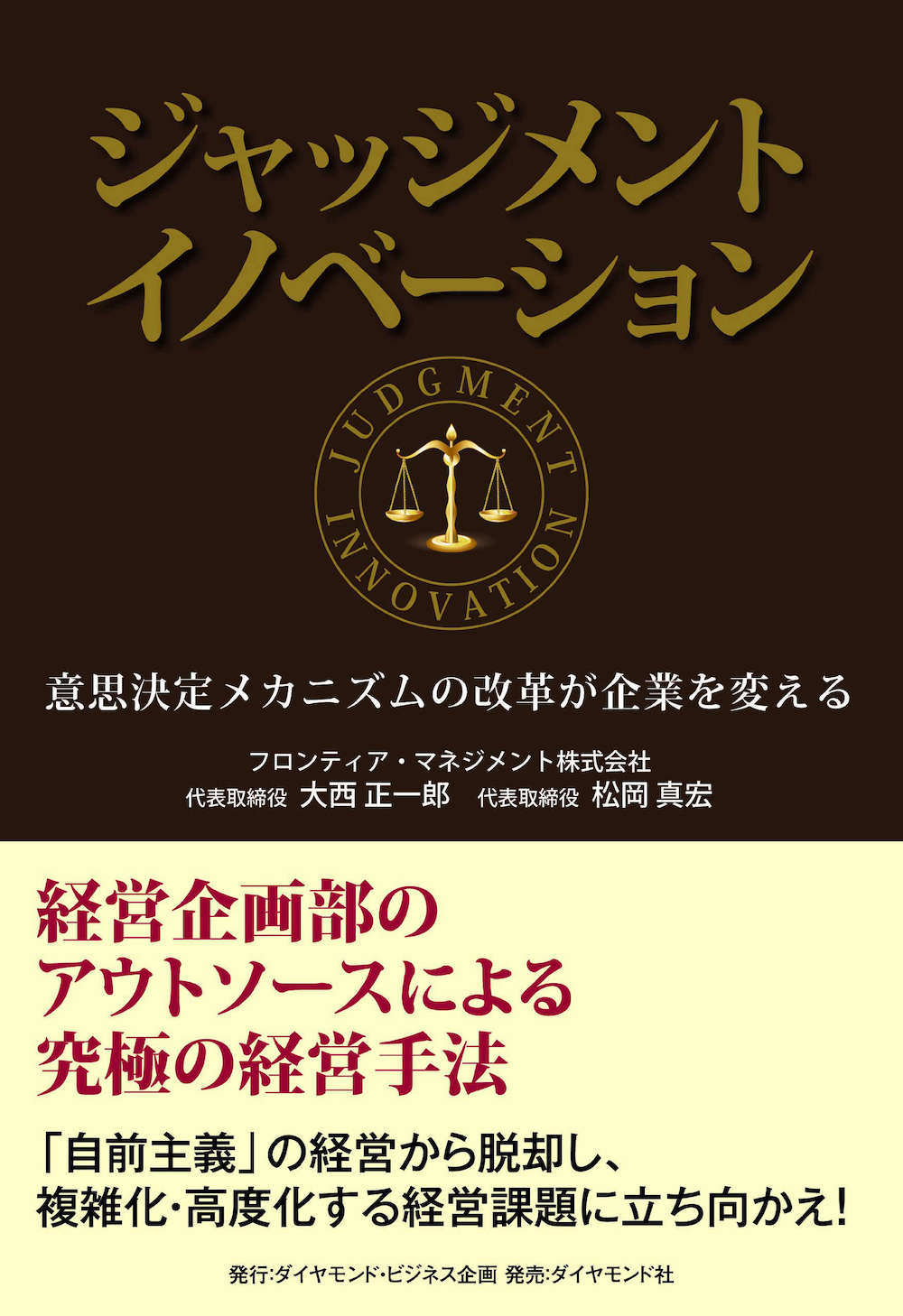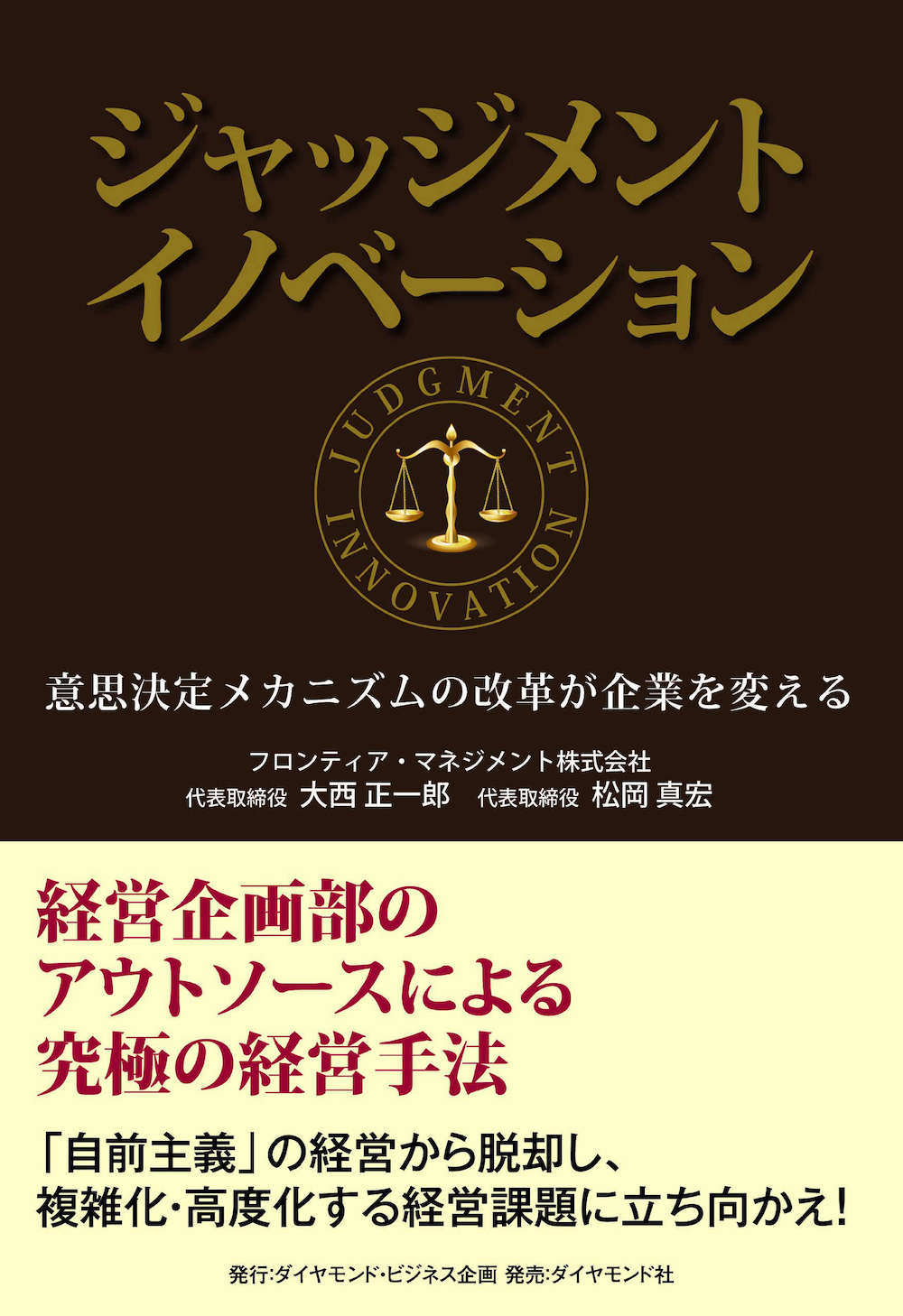――まず、本書を執筆された理由についてお聞かせ願えますか。
大西氏・松岡氏(以下、大西・松岡) グローバル化が進む中、経営課題は複雑化・高度化の一途を辿っており、プロパーの経営陣のみでの意思決定では対応が難しくなってきています。従来型の経営改革では既に限界に来ているのです。その警鐘を鳴らす意味でも、「意思決定」の在り方を体系的に類別し、これからの意思決定の在り方について解説することは、経営に苦しむ多くの企業にとって重要な指針となるのではと考えました。
――お二人は産業再生機構で出会われたそうですが、過去にどのような経営課題に立ち向かわれたのでしょうか。
大西・松岡 企業によって内包する課題は本当に様々です。例えばカネボウでは、経営再建の柱として、不採算事業の切り離しを行ないましたが、その取り組みには大きな困難を伴いました。切り離した事業は繊維部門。カネボウにおいて繊維部門は創業当初から続く本業です。現在では最もメジャーとなった化粧品事業も、当時は傍流という認識でしかありませんでした。不採算事業であった繊維事業を切り離すというこの意思決定は、産業再生機構という第三者機関でなければなしえなかったことでしょう。歴史ある企業であればあるほど「変わる」ということは口で言うほど容易ではありません。内部事情にとらわれない客観的な判断、つまりは「第三者」からの視点の重要性は高まっているといえます。
――経営判断に第三者の視点が重要となっている理由としてどのような社会背景があるのでしょうか。
大西・松岡 冒頭でも少し触れましたが、経営判断が非常に複雑化しているということが挙げられると思います。つまり単一事業の単純な損益の比較だけで解決しうるような課題が減ってきているということです。非常に複雑な法的な観点やグローバル戦略における様々なリスク。例えば店舗撤退ひとつとってもみても、賃貸契約や雇用契約、仕入れ先との契約等、将来おこりうる不確実性など考慮すべき点があまりにも多い。それらをタイムリーに解決していくには、もはや「自前主義」の経営判断では対応できません。
――人材・組織、ITだけでなく法務、会計・税務などの専門家が求められるという点で従来のコンサルティングファームは転換期を迎えているように思われます。
大西・松岡 そうですね。ITから法律、会計まで網羅できるコンサルティングの必要性の高まりは明らかでしょう。従来にはない総合的なコンサルティングファームの有用性を認識したからこそ、フロンティア・マネジメントの存在意義があります。一企業ですべての分野に特化した専門家を備えることは大変難しく、そのために経営判断に際して外部の意見を取り入れることは効果的といえるでしょう。
――最後に本書を手に取られる方へメッセージをお願いします。
大西・松岡 より総合的な判断を行なえる外部の人間の存在が必要不可欠となってきています。私たちはこれを「自前主義からの脱却」と呼んでいますが、是非本書が「意思決定の在り方」について見つめ直していただくひとつのきっかけとして、そして困難を極める経営改革の一助として、皆様のお役に立てれば幸いです。
大西正一郎(おおにし・しょういちろう)
早稲田大学法学部卒業。
1992年に東京弁護士会弁護士登録。奥野総合法律事務所に勤務。
1997年にパートナー弁護士に就任。
2003年に産業再生機構に入社し、マネージングディレクター就任。
2007年にフロンティア・マネジメントを設立し、代表取締役に就任。
松岡真宏(まつおか・まさひろ)
東京大学経済学部卒業。
野村総合研究所、バークレイズ証券会社を経て、1997年に現在のUBS証券会社に入社。
1999年に株式調査部長兼マネージングディレクターに就任。
2003年に産業再生機構に入社し、マネージングディレクターに就任。
2007年にフロンティア・マネジメントを設立し、代表取締役に就任。