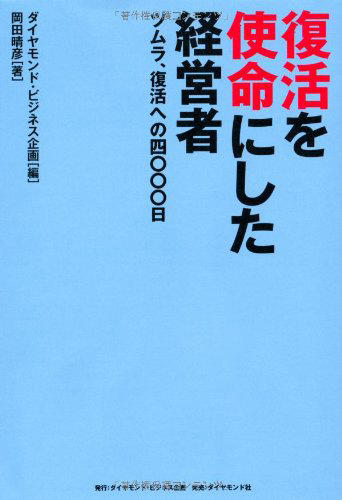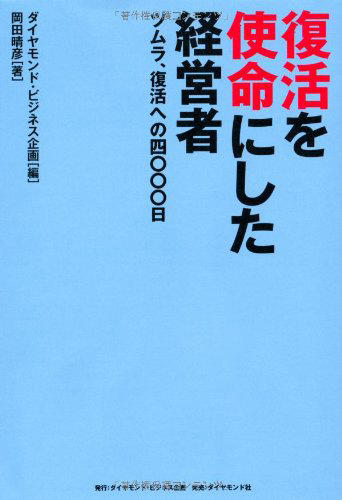――『テクノアメニティ』から約1年。この企業に注目した理由について教えてください。
岡田氏(以下、岡田) 何と言っても劇的な業績回復でしょう。ツムラといえば、明治時代に端を発する老舗の名門。ところが売れ筋の漢方「小柴胡湯(しょうさいことう)」の副作用報道や経営者一族の特別背任疑惑が重なり、連結売上高はピーク時1200億円から3割減。第一製薬から呼び寄せられ改革の指揮を任された芳井順一現会長が、当初全身の体調不良を訴えたというのも肯ける苦境です。そこをどう乗り切って今に繋いだのか。これは経営者として極めて興味深いことです。
――ツムラの経営改革にあたっては、かなり大胆な施策をいくつも打っていますが、中でも印象的なものは何ですか。
岡田 一言で表すとすれば、「選択と集中」ということになるのかもしれません。まず決めて、そして貫く。芳井氏が選んだのは原点回帰。つまり「漢方」でした。そして目指すべき方向性を明確に定めた。文部科学省が医学教育のモデル・コア・カリキュラムに「和漢薬を概説できる」という一文を載せる。このような後押しもあり、何をしなければならないかが自ずと見えてくる。これを大学のカリキュラム担当の教授に理解していただくため、支店長と一緒に最前線で活動するという発想には脱帽せざるを得ません。
――古い組織を変えるということはとても難しいことだとされていますが、なぜツムラは変わり、復活を遂げることができたのでしょうか。
岡田 一番の要因は、当事常務取締役本部長だった現会長の芳井氏自らが率先して動いたことではないでしょうか。組織というものは一からつくることより、古いものを清算し変えていくことのほうがずっと労力を要します。既存の特権を捨て去ることは、ことさらビジネスの世界では難しく、抵抗を生みます。しかし、沈みかかっていたツムラにはもう一円たりとも無駄なことにお金を使っている余裕はなかった。一刻も早く悪しき慣習を捨て去らなければ、会社の未来はない。そんなところまで追い詰められていたのです。
そんな中、芳井氏は率先垂範として一早くその特権を捨て去りました。新幹線も飛行機も、普通の社員と同じ待遇のものにしか乗らない。車も、黒塗りのハイヤーではなく、会社の営業車。通勤も駅まで自転車を漕ぎ、電車で本社まで通う。一部上場企業の常務取締役で本部長までも勤める役員としてはありえないことでした。しかし、そういった芳井氏の自ら率先して実践するという姿勢が、社員たちの心構えをも変えていき、ひいては会社全体を変えていったのです。
――なぜ芳井氏は、商品のコストが上がってしまうリスクを伴ってまで、「生薬トレーサビリティ体制」の確立にこだわったのですか?
岡田 「漢方薬の安全性や信頼性に関わる不透明感を完全になくしたい」という芳井氏の、ツムラに移って以来胸に抱えていた想いがそうさせたのでしょう。それをなくして漢方の未来はないと芳井氏は考えていました。
スーパーで生産者の顔写真入りで売られている野菜のように、漢方薬の原料となる生薬も、すべてが誰にどこの畑で作られ、どのように加工流通されたか追跡管理できるようになれば、安定供給できるばかりか、原料である生薬と製品である漢方の安全性を担保できるようになる。さらには、安定した品質の原料が確保できることで、製品の品質も安定し、薬効の不変性にも貢献できるはずだ、と芳井氏は思っていたのです。
また、社内から「コストが上がってしまったらどう責任をとってくれるんだ!」といった反発の声もありましたが、芳井氏は逆にトレーサビリティを行なえばコストは下がると確信し、社員たちにもそう説明しました。そして実際に、コストは下がったのです。生産から流通の過程を明確にすることで、無駄なものを省くことができたためでした。
「ツムラは漢方においてナンバーワンの会社だ。それなら使っている生薬について責任を持たなくてどうする。安全な生薬でつくった安全な漢方薬を患者様にお届けするのはツムラの使命だ」
そういった芳井氏の確固たる想いが、当事不可能だとされていた生薬のトレサビティ体制の実現を可能にしたのです。
――最後にメッセージをお願いします。
岡田 本書を執筆するにあたって、芳井氏に何度も取材をし、原稿のやりとりを重ねるうちに、不思議な事実が浮かび上がってきました。それは、いくつもの偶然の一致です。芳井氏がツムラにやってきたのも、その後の数々の改革と偉業も、もし何年か違っていればどれも成功する可能性は極めて低かったのではないかということに気がついたのです。
会社を復活させなければならないという使命、そして、多くの患者を救うために漢方を復活させなければならないという使命。そういった様ざまな使命が、芳井氏とツムラの背中を「偶然」という形で押したのではないでしょうか。
今回のことからわかったことがあります。それは人間が自身の「使命」を深く自覚したとき、「使命」に生きようとしたとき、その使命を果たそうとする信念はいくつもの偶然を生み出してくれる、ということです。それぞれの使命を背負ったとき人間は、その人が持っている以上の力を発揮できるのです。さらに、その信念は間違いなく周囲の人を変えていきます。
本書が、自分の「使命」とは何かを見つめなおすきっかけに、少しでもなれたなら幸いです。